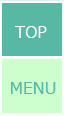人間と同じく、犬や猫も大怪我や手術中の出血、貧血などで輸血が必要になるケースがあります。
現代の医学では人工的に血液を作り出すことはできず、人間の場合には赤十字社などによる献血活動が積極的に行われていますが、獣医療においては献血制度が十分に整備されていません。そのため、輸血が必要な動物の命を救うには、飼い主様の協力が不可欠です。
獣医療の現場では、飼い主様が飼育している犬や猫から血液を提供していただくことや、病院で飼育している動物から血液を分けてもらう取り組みが行われています。
今回は、犬と猫の輸血について詳しく解説します。

輸血が必要となるケース
犬と猫において、輸血が必要となるケースは主に以下の4つです。
・大量出血:交通事故による臓器の破裂や骨髄腫瘍による出血が主な例です。
・重度の貧血:免疫介在性溶血性貧血やバベシア症などによる重度の貧血がこれに該当します。犬では自身の免疫細胞が赤血球を攻撃し、破壊することで重度の貧血が引き起こされることが多く見られます。
・凝固障害や血小板減少症:播種性血管内凝固症候群(DIC)や免疫介在性血小板減少症などが例として挙げられます。
・その他:全身性疾患や低タンパク血症によっても輸血が必要となることがあります。
これらの状況では、輸血以外に有効な治療法がない場合がほとんどです。
供血犬と供血猫の役割と選定基準
獣医療の現場では人間の赤十字社のような組織が存在しないため、輸血用の血液を確保するためには飼い主様の協力が求められます。
また、当院含め一部の動物病院では動物を飼育して、必要に応じて血液を提供してもらうシステムを採用しています。これらの動物を供血犬(きょうけつけん)や供血猫(きょうけつねこ)と呼びます。
しかし、すべての犬や猫でも供血犬、供血猫になれるわけではありません。供血犬や供血猫として選ばれるためには、基礎疾患がなく、理想的な健康状態であることが求められます。
また、これらの動物の福祉を尊重し、ストレスのない環境を整えることが極めて重要です。そのため、多くの供血犬や供血猫は病院スタッフによって家族同様に愛情を込めて飼育され、病院の一員として活動しています。
犬と猫の血液型と交差適合試験
人間同様に、犬と猫にも血液型が存在します。
<犬の場合>
犬の血液型は非常に複雑で、DEA(Dog Erythrocyte Antigen=犬赤血球抗原)式に基づき、DEA1.1、DEA1.2、DEA3からDEA13まで13種類以上があります。
1回目の輸血時は異なる血液型でも大きな問題は起きにくいですが、2回目以降の輸血では異なる赤血球抗原によって重篤な拒否反応が発生することがあります。
理想は同じ血液型の犬から輸血を行うことが望ましいですが、犬の血液型は13種類以上で完全な一致は稀であるため、問題となるDEA1.1のチェックだけは必ず行います。
輸血前には上記の血液型判定に加えて、ドナー(供血犬・猫)とレシピエント(血をもらう犬・猫)の血液を1滴ずつ混ぜて行うクロスマッチテスト(交差適合試験)を実施し、拒否反応が起こらないことを確認します。
<猫の場合>
猫の血液型はシンプルでA、B、AB型の3種類のみであり、日本にいる猫は遺伝的にA型が多く、B型は少数、AB型はほとんどいません。なお、猫の輸血には初回から細心の注意を払う必要があります。特にA型とB型の相性が悪く、A型猫の血をB型の猫に輸血すると重症の急性溶血反応を起こし、命にかかわることがあります。
猫も犬と同様に、血液型の判定とクロスマッチテストを行い、輸血の安全性を確保しています。
輸血の実施手順
1. ドナーの健康状態の確認
輸血を行う前には、まずドナーの健康状態を確認するために身体検査や血液検査を行い、安全に血を採取できることを確認したうえで採血を行います。
2. 採血とその後の処置
ドナーからの血液後は必要に応じて皮下点滴を行い、ドナーの体調を安定させます。採取した血液は無菌的な方法で冷暗所に保管されます。
3. レシピエントの準備と輸血の実施
レシピエントに対しては、輸血を行う前に血液型判定とクロスマッチテストで安全に輸血できる血液を判断したうえで、静脈からゆっくりと輸血を行います。
4. 輸血後のケア
輸血後2〜3時間は病院内で安静にして、急性溶血反応や拒否反応、嘔吐などの異常がないかを観察します。また、輸血当日の激しい運動は控えるようにしてください。
5. 継続的なフォロー
一度の輸血で状態が改善することもありますが、免疫介在性溶血性貧血などの場合は、複数回の輸血が必要なこともあります。
輸血を実施する動物病院の現状と課題
現在、輸血を実施できる動物病院は減少傾向にあります。
これは輸血を経験したことのない獣医師の数が増えていること、血液を安定して供給できる中〜大型犬の飼育頭数が国内で減少していること、採取した血液を管理する際の手間やコストの増加などが考えられます。
特に血液の確保と管理の難しさは獣医療における大きな課題となっています。
将来的にiPS細胞から血液(血小板)を作る技術が確立されれば、人工血液の開発が可能となるため、新たな研究分野として期待されています。この技術の進歩が、輸血が必要な多くの動物たちの命を救う手段となるかもしれません。
当院に紹介される輸血症例の特徴と対応方針
当院には、輸血が必要な患者様にご来院いただくことがあります。
飼い主様の多くは輸血が可能なかかりつけの動物病院をお持ちではないため、大学病院などの二次診療施設から当院をご紹介いただき来院いただくケースがあります。
まとめ
輸血は、重度の貧血や大量出血で苦しむ動物たちを救うための唯一の治療法です。
当院でも輸血用に供血犬を2頭、供血猫を1頭飼育しているため、緊急時にも迅速な対応が可能です。
また、輸血時といった緊急時だけでなく、通常の診察においても患者様のご要望に合わせて臨機応変に対応しております。
当院は輸血において今後も力を入れていきたい分野の一つだと考えており、多くの命を救うために尽力を続けています。お困りの際はお気軽にご相談ください。
埼玉県さいたま市浦和区 結城チロロ動物病院

 048-884-1211
048-884-1211